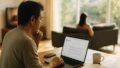「定年後、何をして生きていく?」
退職後の朝は静かです。仕事のメールは来ません。
うれしいはずの自由時間なのに、ふと「この先、何をして生きていく?」が頭から離れない。
年金だけでは少し不安。
子や孫には“まだ現役だよ”と胸を張りたい。
社会とのつながりも切らしたくない。
——そんな気持ち、よくわかります。
僕も55歳で会社を離れ、家事を分担しつつ、ぽっかり空いた時間と向き合いました。
そこで見つけたのがAIを“難しい道具”ではなく“日常の相棒”にするやり方です。
最初はPCとスマホだけ。
専門知識はゼロから。
けれど生活費のムダを減らす、在宅でできる仕事のタネをつくる、人に喜ばれる小さな支援を増やす——この3つが少しずつ形になりました。
この記事は、その道のりをリアルな体験談と、後半で紹介するDMM WEBCAMP (AIコース)の情報にわけて、あなたの「次の一歩」につながるよう、書いていきます。
\やりたいことは明確、迷いはないなら/
退職後にAIを“日常の相棒”へ|B5チラシ・メルカリ・家族LINEで実感した小さな変化
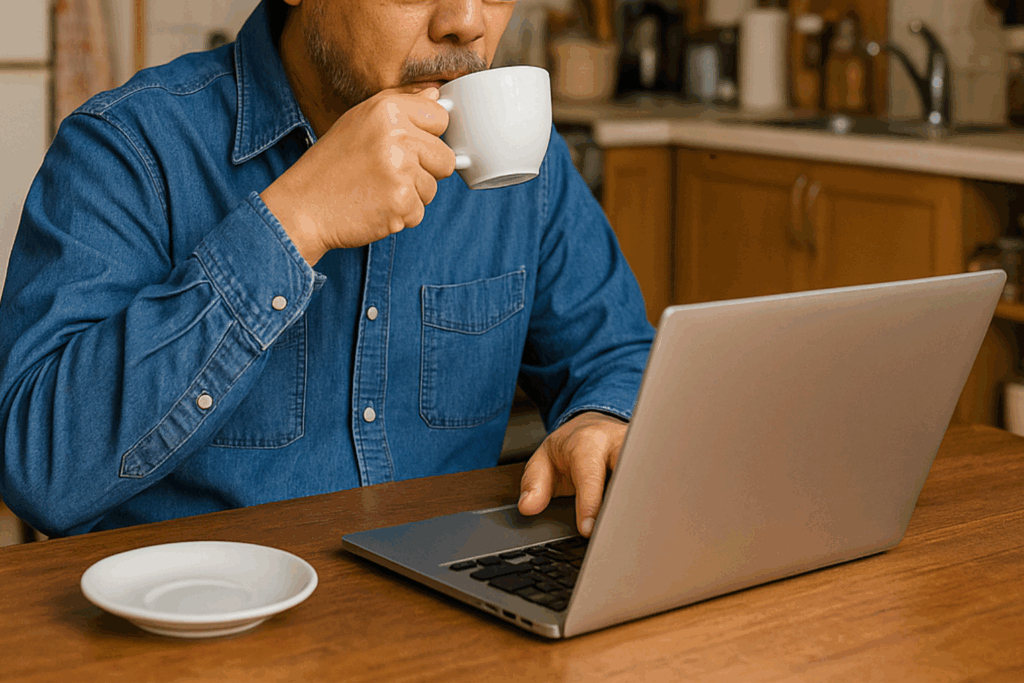
退職して最初の1週間、僕は掃除機をかけながら考えていました。
「今日、誰に会うでもない。メールも来ない。時間はある。でも、この時間で何ができるだろう」。
韓ドラの“言い回し”をAIで確認:伝わる楽しさが最初の一歩
その日の昼、妻が見ていた韓国ドラマの感想をスマホに打ちながら、ふとAI翻訳を開きました。
字幕で拾えなかったニュアンスをAIに聞くと、自然な日本語で「ここは皮肉だよ」と教えてくれる。
妻が「これ、ブログで残せたら楽しいね」と笑う。
“楽しさ”と“役に立つ”が初めてつながった瞬間でした。
メルカリの「傷の説明」を丁寧に:固定フレーズ化で出品ストレスが消える
別の日、家の不用品をメルカリに出そうとしたとき、商品説明文に悩んでAIに相談。
使い込んだカメラの「傷の説明」を、買い手に失礼なく、でも正直に書く言い回しを提案してくれる。
相手の不安が減る文章が1分で出てくるので、出品が一気に楽になりました。
旅程比較は表で即決:迷いが減る“見える化”のコツ
旅行の計画も変わりました。AIに旅程の比較表を作ってもらうと、ホテルの立地・移動・食事の目安を表形式でざっと整理してくれる。
「結局どれが合っている?」という迷いが短時間で解ける。
家族LINEを“角の立たない言葉”に:関係がギクシャクしない小ワザ
帰ってきたら、LINEで子どもに旅の報告。すると子どもがひと言。
「その文、AIで柔らかめに直して送ったら?」。
やってみたら、家族LINEがぎくしゃくしない。
些細なことですが、暮らしの空気が変わりました。
僕は在職中、人材育成やシステム導入に関わった経験があります。
だからわかるのは、道具が人を助ける時は、“難しいか簡単か”ではなく“生活や仕事の動きに自然に溶けるか”が本質だということ。
AIはまさにそれでした。
図書館のミニ講座で二刀流スタート:在宅×地域の頼まれごとが増えるまで
「調べる・書く・整える・伝える」の4つが速くて丁寧になる。
気づけば、この小さな改善を組み合わせて、在宅で無理なく続けられる“新しい仕事”のかたちが見えてきました。
地域の図書館に相談し、“写真整理とAI活用のミニ講座”を1時間だけ開いてみました。
古い写真をAIできれいにする手順、町内会だよりの下書きを整えるコツ、スマホだけでできるAI翻訳の使い方。
参加者は10人ほど。
終わってから「次はうちのサークルでもやって」と声をかけられました。
小さく始めると、次の小さな声が届く。
ここから、在宅の作業+地域の手伝いという“二刀流”が少しずつ根づいていきます。
退職後 AIスキルで新しい仕事|家の机で始める「B5回覧・CSVグラフ・家族LINE」の小仕事

朝:回覧文をB5・14ptで“読みやすく”——高齢者に届くレイアウト最小ルール
コーヒーを置いて、僕は父の回覧文を開きます。AIに「高齢の方でも読みやすく」と頼むと、固い言い回しがやわらぎ、B5の紙に収まります。見出しを太く/本文は行間を広めに。最後に電話番号を14pで。印刷した1枚を父に渡すと、「これなら配れるな」と肩の力が抜けます。
昼前:中古カメラの“傷”——不安にさせない3行と固定フレーズ化
押し入れから出てきた古いカメラ。
キズの説明で手が止まり、AIに「正直で不安にさせない表現を3案」と投げると、〈作動に影響なし/写真3枚目参照〉などの固定文が出て、出品が数分で片づきます。
夕方:会計CSV→不要列カット→棒グラフ1本——会合の“冒頭2分”を静かに
町内会の会計CSVを開き、不要な列を消して棒グラフを1本。
数字が紙で通るだけで、会合の冒頭2分が静かになります。
夜:家族LINEは“角の立たない言い回し”——返信の温度を上げる小ワザ
家族LINEに旅の報告を送る前に、AIで角の立たない文に整えると、返事の温度が少し上がります。
4コマで完了:開く→頼む→整える→保存——在宅ワークに変わる“家事の延長”
「開く → 頼む → 整える → 保存」の4コマで終わる、小さな家事の延長です。
でも、その小さな完了形が1つ増えるたび、次の「お願いできますか?」が近づきます。
- 開く:回覧文/出品画面/CSV/LINE下書き
- 頼む:やさしい言い回し/正直で不安にさせない説明3案/棒グラフ化/角の立たない文
- 整える:B5レイアウト・太字と行間/固定フレーズ採用/不要列カット→グラフ1本/語尾をやわらかく
- 保存:PDF1枚/テンプレ保存/印刷用の紙/送信前の下書き
行き当たりばったりより、ひと続きで身につけると迷いが減る
行き当たりばったりでも回せますが、頼み方の型・表と図の作法・間違いの確かめ方をひと続きで身につければ、迷いはもっと減るはず。
ここから先は、退職後でも無理なく続く「学び方の設計」をかんたんに確認していきます。
“続けやすさ”“何をどの順で学ぶか”“最初の出口”を、条件に合わせて照らし合わせます。
「退職後×在宅」で回るAI基礎体力をどう積む?“学び直しの迷子”を防ぐ設計|DMM WEBCAMP(AIコース)
- 続けやすさの仕組み:週2回×25分の個別面談+いつでも質問できるチャット+学習の見える化で、ひとり学習の挫折を減らす。
- 学ぶ中身の射程:Python(道具の基本)→ 表を整える道具 → NLP(文章の整理術)→ 深層学習(写真の見分け方の基礎)→ 仕事での活かし方までを一筆書き。
- 自分の予定に合わせやすい:4/8/12/16週間の期間から選べる。未利用期間の返金の考え方も明示。
- 制度:最大70%のキャッシュバックに関する説明あり。ただし現に雇用され転職を目指す方など条件付き。退職後にそのまま当てはまらない場合あり。
1. AIで何が“楽”になる?:回覧・出品・会合資料を早く丁寧に仕上げる
AIで速くなる4つの場面
- 調べる:要点の要約、比較のたたき台(旅行プラン、商品の違い、会合メモ など)
- 書く:案内文・商品説明・依頼メール・ブログ草稿の下書き
- 整える:誤字、敬語、読みやすい構成、表や簡単な図で見える化
- 伝える:やさしい言い回し、翻訳、箇条書き→B5チラシの下地
このコースの射程(入門〜初級)を生活に近い身近な言葉で
- Python=「道具の基本操作」
- Numpy / pandas / matplotlib / Keras=「表をきれいに整える/数字をグラフにする/画像に触れてみる道具」
- 自然言語処理(NLP)=「長文を要約・分類する“文章の整理術”」
- 深層学習(画像側)=「写真や手書き文字の“見分け方”の基礎」
- 業務での活用=「どこまでAIに任せ、どこから人が直すかの線引き」
こうした章立てが公式に明記されているため、“何から始めれば?”迷子を避けやすいのが特徴です。
\やりたいことは明確、迷いはないなら/
2. 不安と対応を1対1で:ゼロから・年齢・独学・収入化の“壁”をどう越えるか
不安A:PCやAIはゼロからで本当に大丈夫?
- コースの仕組み:週2回×25分のマンツーマン面談とチャット質問(原則24時間以内回答)、進捗の見える化。“一人では続かない”を外側の仕組みで補う。
- 生活に落とすと:つまずいたら待たずに聞ける。表の作り方/言い回しのやわらげ方/図の入れ方の小さな疑問をその場で片づけやすい。
- 注意:タイピング/コピー&ペースト/保存は毎日10分の反復が近道。
不安B:年齢的に遅くない?若い人ばかりで浮かない?
- コースの仕組み:オンライン中心+個別面談。学びの型(自己調整学習の3ステップ)で自分のペースに落としやすい。
- 生活に落とすと:家事・通院・地域行事に学習スロットをはめやすい。社会経験の長さが文書の整え・依頼文の配慮で強みになる。
- 注意:ツール名は入れ替わる。原理と型を押さえる姿勢が肝心。
👉 年齢不安を具体的に解くチェックポイント
年齢の不安は多くの方の共通点です。
▶︎40代以降の学び直しの現実(支援・注意点の整理)も参考になります。
不安C:AIに聞けば出るのに、わざわざ学ぶ意味ある?
- コースの仕組み:「頼み方(プロンプト)」の型とAIの限界の学習。誤り前提の検証(比較・出典確認)まで含む。
- 生活に落とすと:メルカリ説明文や町内会の案内で何案か出して良い所取りできる“作法”が身につく。
- 注意:狙いは100点の自動化ではなく、下書きの高速化+人の最終判断。
不安D:独学でもいけるのでは?
- コースの仕組み:各章の課題→レビュー→最終課題/ポートフォリオで、締切があるから続くを担保。
- 生活に落とすと:「B5チラシ1枚を完成」など完了形の成果物が定期的に残る。
- 注意:課題は自分の現実(家・地域・副業)に寄せて設定すると、後でそのまま使える。
不安E:在宅の小さな収入につながる?
- コースの射程:文章整え/比較表/資料化など “小さな請負テンプレ” に直結する練習が多い(章立てに該当項目が並ぶ)。
- 生活に落とすと:会計説明の“見やすい表”、サークル案内、家計CSVの見える化など、月2〜4件の小仕事のタネに。
- 注意:最初は“お金より実績”。無償〜少額で2〜3件の成果と感想を積むと、次に進みやすい。
3. むずかしい用語を“身近な言い方”に:pandas=表を整える/NLP=文章の整理
| (公式記載の例) | 生活語でひとこと | 使い道の例 |
|---|---|---|
| Python | 道具の基本操作 | 家計・会計CSVの並べ替え |
| Numpy / pandas / matplotlib / Keras | 表を整える・数字をグラフにする・画像に触れる | 会合資料の1ページ目を見やすく |
| 自然言語処理(NLP) | 長文の要約・分類(文章の整理術) | 町内会だより/ブログの整え |
| 深層学習(画像) | 写真や手書き文字の“見分け方” | 古い写真の整理・ラベリング |
| 業務での活用方法 | 人とAIの分担の線引き | 在宅の品質管理ルール作り |
📌 これらはコースページに章ごとの説明が明記されています。生活の中の身近な題材で練習→実務に寄せる順番が取りやすい構造です。
4. 学習サポートと期間:4/8/12/16週の“家の予定に合わせる”選び方
- 支援:週2回×25分のメンタリング/チャット質問は原則24時間以内回答/進捗の見える化システム。
- 期間:4・8・12・16週間から選択(中身は同一で学習ペースの違い)。
- 返金の考え方: 未利用期間の返金(4週単位/4週間プランは除外)の案内。急な家庭都合にも備えやすい。
チェック(5分で照合)
- 期間は家の予定と重ならないか(4/8/12/16週のどれ?)
- 面談の曜日・時間が合わせられるか/チャットの返信目安を理解したか
- Python→表→文章→画像→活用の順で意味が通ることを確認
- 返金条件(4週単位・除外あり)を理解したか
5. 制度の読み方:キャッシュバックは“使えたらラッキー”で判断する
- 最大70%キャッシュバックなどの制度説明があるが、対象は“現に雇用され、転職を目指す方”など条件付き。退職後にそのまま対象外のケースが普通にありうる。該当可否は必ず確認。
- 考え方:制度は“使えたらラッキー”。使えなくても、日々の時短×小さな実績で受講費の回収計画は組める。
6. 「最初の出口」をひとつ決める(完了条件まで書く)
| 最初の出口(1〜4週間で到達) | 4コマ手順(開く→頼む→整える→保存) | 完了条件 |
|---|---|---|
| B5チラシ1枚(案内+表) | Wordを開く → 本文をAIでやわらかく → 表を1つ入れる → PDF保存 | PDFが1枚できたら完了 |
| メルカリ出品テンプレ3種 | 出品ページ → タイトル/説明/注意点をAIで3案 → 写真に合わせて微調整 → 出品 | 3ジャンル分を登録 |
| “暮らし×AI”ブログ4本 | テーマ決め → 下書きをAIで叩き台 → 見出しと表を整える → 公開 | 週1本×4週 |
| CSVの見える化 | 家計/会計CSV → 不要列を削除 → 棒 or 折れ線作成 → 画像書き出し | グラフ1個が会議で使える |
📌 コツ:渡し先(家族/町内会/サークル)を最初に1人だけ決める。実在の相手がいると、学びが迷いません。
7. 小さな収入の見立て:月2〜4件で回収する現実ライン
| 小さな仕事の例 | 単価の目安 | 月の件数 | 月の合計 |
|---|---|---|---|
| 案内文のリライト(B5チラシ) | 2,000〜5,000円 | 2〜4件 | 4,000〜20,000円 |
| 会計資料の見やすい整形 | 3,000〜8,000円 | 1〜3件 | 3,000〜24,000円 |
| ブログの下書き整え(1本) | 3,000〜6,000円 | 2〜3件 | 6,000〜18,000円 |
📌 最初は“実績づくり優先”で無償〜少額を2〜3件。成果物+感想の声が次の依頼につながります。
8. 生活×在宅に寄せるほど強みが活きる理由|“AIコースである必要”の判断軸
- 即効性:文章整え・表と図・翻訳・要約は当日から生活で使える。
- 迷子防止:Python→表→文章→画像→活用を一筆書きで学べる。
- 続ける仕組み:個別面談/チャット/見える化が “続かない”問題 を抑える。
- 逃げ道:未利用期間の返金の考え方が明示され、家庭の突発対応に備えられる。
📌 逆に:数式の深掘りや大規模モデルの研究を最初から狙うなら、他の設計がよい。生活×在宅の現実路線ほど、このコースの強みが活きる。
9. 申込み前ミニチェック(Yes/Noで30秒)
- 今の自分の目的は「在宅の小さな請負」or「ブログ運用」or「再就職の準備」のどれかに絞れている
- 最初の出口をひとつ決めた(上の表から選ぶ)
- 期間(4/8/12/16週)を家の予定と突き合わせた
- 面談の曜日・時間とチャットの返信目安を理解した
- 返金条件(4週単位/4週プラン除外)と制度の対象条件を確認した
10. 1分でわかる要点:「退職後×在宅」で回るAI基礎体力の積み上げ!
- 公式ページで期間・支援・返金・制度を自分のカレンダーと照合(5分)。
- 最初の出口を1つだけ決める。
- 45分×3コマ/週の学習スロットを先に確保する(家の予定に重ねると続きやすい)。
📌 制度は“使えたらラッキー”。使えなくても、日々の時短×小さな実績で回収できます。
\やりたいことは明確、迷いはないなら/
気になった“もやもや”、不安をほどくQ&A

1. 「退職後 仕事ない」——ほんとうに“ない”のか?
気持ち:「求人を見ても、若い人向けが多い。自分にできることって何?」
事実に近い見方:“正社員の新しい専門職”はたしかに狭い。でも、在宅の“頼まれごと”や週1〜2回のサポート業務は細かく点在しています。
僕の試し方
- 身近な団体(町内会・図書館・サークル)に「案内文をやわらかく直す」「B5のチラシを作る」をサンプル1枚で見せる。
- “無料でいいので1枚やらせてください”から始める。成果物+喜びの声が次の依頼につながる。
小さな出口(今日できること) - 昨日のメモやお知らせをAIで丁寧な文に直す → WordでB5化 → PDFにする。1枚=仕事の名刺になります。
2. 「AI 難しい」——どこが難しいと感じた?
よくある壁
- 頼み方(プロンプト)が曖昧で、出力がブレる
- 専門用語が連続してやる気が削られる
- “完了形”が見えないから、何をもって終わりか分からない
生活の言い換え - プロンプト=「相手(AI)への指示書」
- NLP=「長文の整理術」
- 深層学習=「写真の見分け方の基礎」
“完了形”の固定(4コマで必ず終わる)
- 開く → 2) 頼む → 3) 整える → 4) 保存
例:案内文なら、Wordを開く/AIにやわらかい言い回しを頼む/表を入れる/PDF保存。これで完了。
3. 在宅でお金をいただく線引き、どの作業から“有料”にしてもいい?
不安の中身
- 知らない人とのやり取りが怖い
- トラブル対応が不安
- 自分の時間が取られるのが嫌
現実的な対策 - “相手を知っている”小さな世界から始める(町内会/サークル/知人)
- 価格より先に“範囲と納期”を明文化(B5片面/3日以内/2回まで修正など)
- テンプレを持つ(依頼の流れ・納品の型・お礼の一言)
テンプレの素(コピペOK) - 依頼受け:「B5の案内文(片面・表1つ)を3日で作成します。2回まで修正可能です。」
- 納品:「PDFとWordの2つをお渡しします。次回は日時と会場だけ差し替えれば使えます。」
- お礼:「また日程が決まったら、同じ型で素早く作ります。」
4. プログラミングまで要る?“表と図”だけで人の役に立つ現実ラインを教えて。
よくある落とし穴
- 数式や理論に寄りすぎて挫折
- 最初から大きなアプリを作ろうとして折れる
線引き - 最初の4週間は“表と図”に限定(家計CSVや会計CSV/棒グラフ1つ)
- 次の4週間で“文章の整理術”(要約・敬語・説明の順番)
- 画像や深い部分は“触ってみる”だけで十分
判断の軸:“生活に戻せるか?”がYesなら続ける。Noなら戻る。
僕の例:旅行プラン比較を表で3案→家族LINEに1つだけ提示→決定が早くなり、ケンカが減る。これで続ける意味が生まれました。
5. 「セカンドキャリア/知的資産」——経験を“言語化”して道具にする
知的資産=長年の暗黙知(例:気まずくならない言い回し、現場の空気の読み方)
AIの役割:あなたの暗黙知を“型”に変える手伝い
- 営業経験→断りメールのテンプレ
- 製造経験→安全手順のチェックリスト
- 家庭運営→買い物・献立の週次テンプレ
やり方
- 自分の経験を箇条書き(3つだけ)
- AIに“配布できる型”に直してもらう
- WordでB5テンプレ化 → 次回は差し替えで使う
効果:再現性が上がる。小さな請負にそのまま転用できる。
6. 「シニア世代と学び直し」——体力ではなくペース設計
前提:1日3時間より、45分×3コマ/週が続く
設計のコツ
- 朝の静かな時間に45分×1(学習)
- 昼の空き時間に15分×2(復習とメモ)
- 週末の午前に45分×2(課題と振り返り)
ツールの変化が速くても、原理と型は変わらない。“頼み方の型/表と図/文章の整理術”に学習を寄せると、道具が入れ替わっても動じないです。
7. 今日からの“3アクション”(迷ったらここだけ)
- 昨日のメモをB5に:AIで丁寧に→WordでB5化→PDF保存
- メルカリ3テンプレ:カメラ/本/衣類の説明文をAIで3案ずつ→Googleドキュメントに保存
- CSV1個の見える化:家計CSV→不要列カット→棒グラフ1本→画像保存
📌 完了の合図:PDF1枚/テンプレ3つ/グラフ1枚。これで1週間の学びは回収できます。
退職後のAIスキルで“新しい仕事”に近づく3ステップ|続けやすさ・学ぶ順番・最初の出口を決める
退職後の不安は、「仕事がない」ではなく「完了形が見えない」から生まれます。
AIは“日常の相棒”。頼み方の型/表と図/文章の整理術を小さく習慣化すれば、在宅の頼まれごとは自然に増えます。
学ぶ場所は、ひとりでは続かないを仕組みで補えるところを選ぶのが近道。
\やりたいことは明確、迷いはないなら/

名前: 桑原仁志|退職後にAI学び直し
肩書: 元・中小企業で人材育成とシステム導入に携わる/現在は家庭と地域活動にAIを応用
一言:「AIは特別な人だけのものじゃなく、暮らしや人とのつながりを広げる道具になる」
55歳で会社を退職後、家事を妻と分担しながら、地域サークルで会計や広報を担当。 孫のアルバム作りや家計簿の整理、サークル案内文など身近な場面でAIを活用。 在職時にも人材育成やシステム導入を経験し、「AIを学べば家庭でも地域でも役に立つ」と実感。 『50代からでも遅くない』を行動で示せるよう、毎朝30分の学び直しを3年継続中。